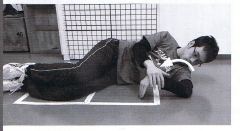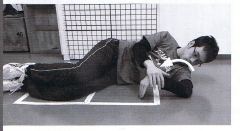☆ケガの予防[障害とメディカルチェック-1-]
まず、バドミントンをやっていて多いケガは「スポーツ外傷(急性外傷)」と「スポーツ障害(慢性外傷)」に分けられる。
スポーツ外傷(急性外傷)は、ねんざや打撲、肉離れ、、関節の靱帯損傷などがあり、スポーツ障害(慢性外傷)には
関節炎や筋炎などがある。
どちらも件数を減らすよう努力することが必要だが、特に、スポーツ障害は繰り返しのストレスで起きるケガなので、その繰り返しのストレス
をコントロールすれば防ぐことが可能だ。
ケガを予防するには、ケガの起きる原因を把握し、対策を立てることが大切となる。
今回、ヒザのケガでも深刻な前十字靱帯損傷とバドミントンで多い肩のケガを取り上げてみる。
●前十字靱帯損傷・・・深刻なケガのひとつで、大腿骨外側から頸骨(すねの骨)の内側に向かって付いている前十字靱帯が断裂する
ということは、ヒザの中でねじれ動作が起きていることになる。
ヒザはもともと「曲げる」「伸ばす」だけでなく、「ひねる」という動きもある。そこによくない動き
が含まれることでケガが発生する。次のフォワードのランジで確認してみよう。
→立位で前に一歩踏み出してみる。踏み出した側の足に体重をかけて観察する。

つま先が外側で、ヒザが内側に向くとヒザにはもっともイヤなストレスを与えてしまう。
このイヤなストレスが続くと前十字靱帯や内側側副靱帯の伸張、断裂につながっていく。
さらに、足の形(扁平足、外反母趾、回内足)や尻に筋力がないなどが重なるとケガの危険性は高まってくる。
フォワードのランジの動きの中で、つま先とヒザの向きを同じにすることや、尻の筋肉を刺激する種目の後で実施すると効果が上がる。
●肩のケガ・・・肩関節の構造は複雑で、重要なのは肩関節を構成する鎖骨や肩甲骨の自由度があるかどうかだ。
腱板という4つの筋肉の筋力も必要だが、まず、柔軟性に留意しよう。
次のスリーパーストレッチで確認してみよう。
→横向きに寝て、下側のヒジを床に着けて90度に曲げる。そのまま指先を床につけるように肩をひねる。
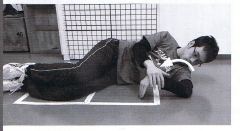
利き手も逆も床に指先が着けばOK。もしできなければ肩の可動域が狭いことを示し、可動範囲の改善を図ることで
ケガの予防ができる。
上の二つの結果はどうだった? スポーツ障害の原因は、練習時間が長すぎたり、同じ動作を繰り返し続けたりといったことだけでなく、
自分の体(動き)に問題があることも多い。
今回のフォワードのランジにおいて「悪い動き」が見られる状態で練習を行えば、当然ながらケガのリスクは高まってくる。
こうした問題のある動きや柔軟性の欠如をトレーニングして改善していくことが必要となってくる。
技術を支える体力を向上させることがケガの予防には非常に有効だ。
ケガの予防 ケガの予防-2-も参考に
▲戻る